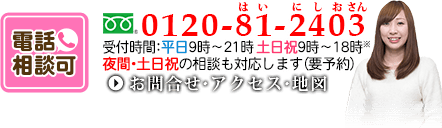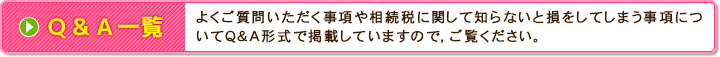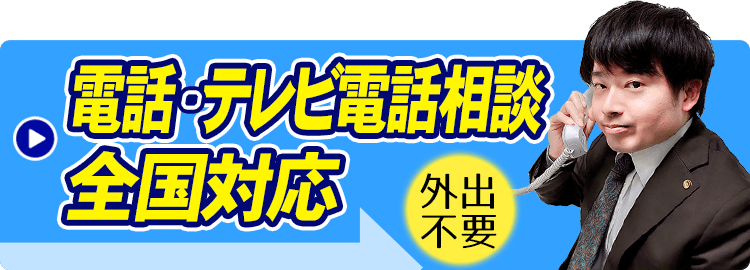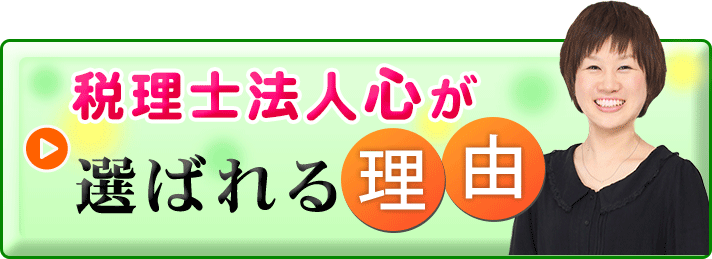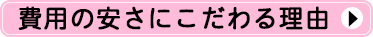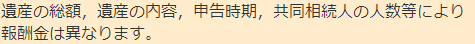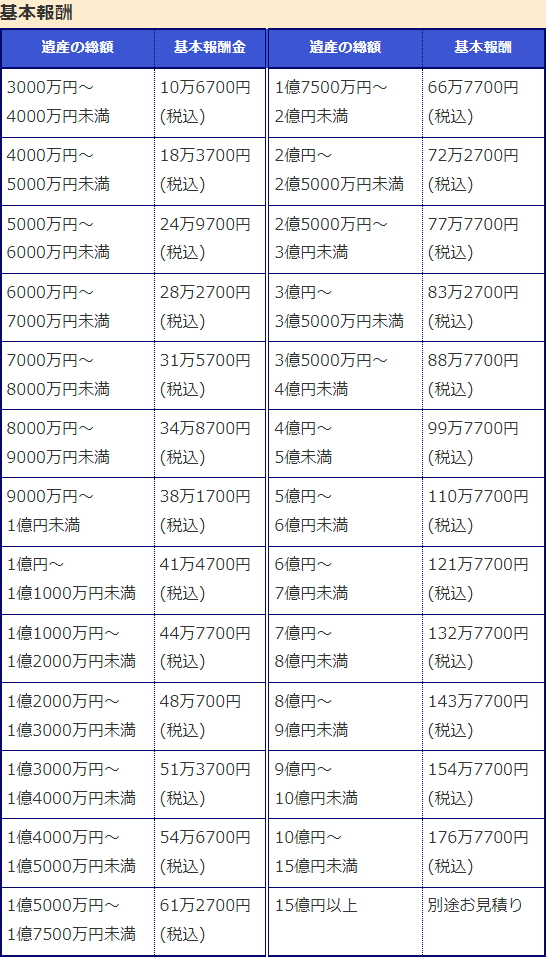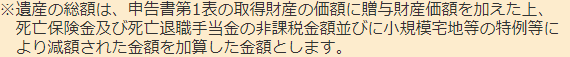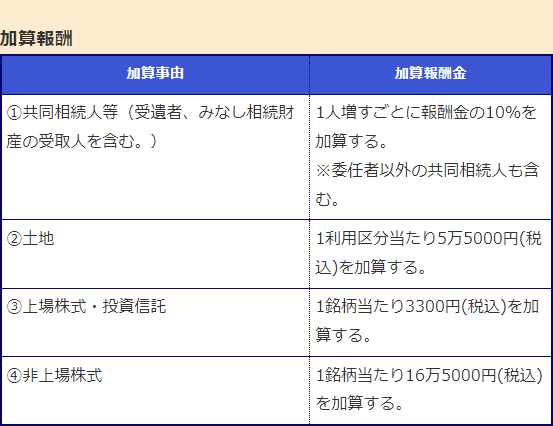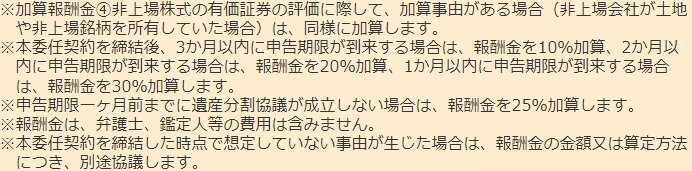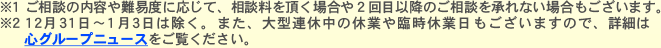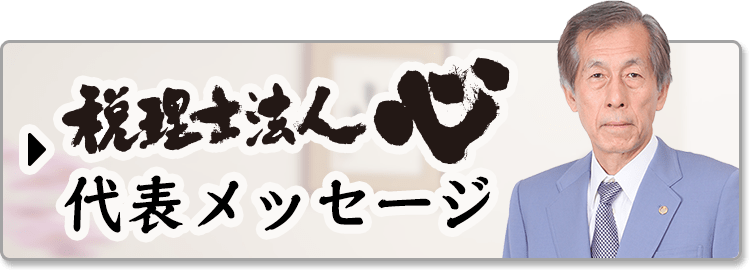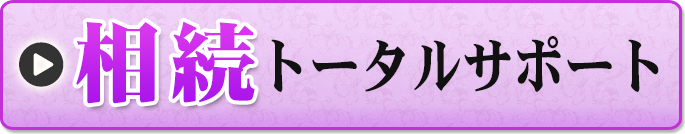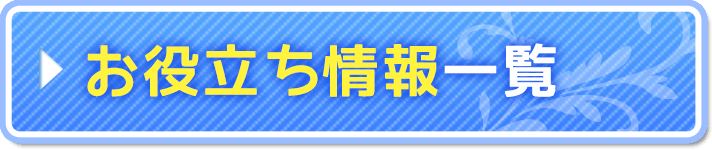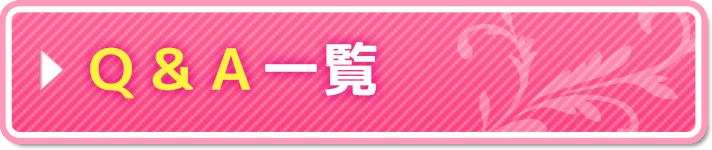「相続税申告」に関するお役立ち情報
相続税申告をするために最初に行うこと
1 相続税申告の前準備
相続税の申告をするにあたり、まず行うべきことは、大きく分けて3つあります。
①遺言書の有無の確認、②相続人の調査、③遺産内容の把握・評価です。
それぞれの確認作業や調査の方法等について、以下で詳しくご説明いたします。
2 遺言書の有無の確認
⑴ 遺言書の有無の確認方法
遺言書があれば、原則としてそこに書かれている内容どおりの分割方法で相続税申告書の作成と相続税納付を行うことができますので、まずは遺言書の有無の確認を行います。
遺言書で、実務上よく見られるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は、自宅の金庫や銀行の貸し金庫に入っていることが多く、被相続人が生前に相続人に預けている場合もあります。
このような場合は、遺言書を開封する前に検認の申立を行う必要がありますので注意が必要です。
ただし、法務局に自筆証書遺言を保管してもらっている場合には、検認の申立は不要となります。
公正証書遺言は、全国の公証人役場で、その有無を検索し照会することができます。
また、公正証書遺言は検認の申立を行う必要がありません。
⑵ 遺言書が存在しなかった場合の対応
遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が何を相続するかを決める必要があります。
相続税申告の提出期限までに遺産分割協議が完了しなければ、いったん法定相続分で相続を行ったものと仮定して、相続税申告書の作成と相続税の納付を行い、後日修正申告(または更正の請求)をしなければなりません。
このように、遺言書の有無によって相続税申告をするために必要となる手続きの内容が変わってきますので、初めに確認を行っておくことはとても重要です。
3 相続人の調査
遺産分割協議が必要な場合、相続人が一人でも欠けた状況で行うと、その協議で決まった内容は無効となってしまい、やり直しが必要になるなどのトラブルが発生します。
また、法定相続人の数は、相続税の基礎控除額の算出や生命保険の非課税枠の算出にも必要になってきます。
そのため、戸籍謄本類を被相続人の出生から死亡まで連続したものを収集し、相続人を正確に調査しなければなりません。
場合によってはより多くの戸籍を収集する必要もありますので、どこまでの戸籍が必要になるのか分からずご不安な方は、一度ご相談ください。
4 遺産内容の把握・評価
相続税の金額を正確に計算して申告・納付するためにも、遺産の内容を正確に把握する必要があります。
遺産の内容を把握するためには、被相続人が生前に持っていた通帳を確認したり、被相続人宛に届く金融機関等の書類を確認した上で各金融機関等に問い合わせたりします。
また、自宅の金庫や貸し金庫に、保険証書や土地の権利証を保管している場合もあります。
そういったものを手掛かりに、被相続人の遺産の内容を把握します。
また、遺産の中に土地や非上場株式が含まれている場合には、相続税評価額を算出する必要があります。
このように財産には様々な種類のものがあり、さらにこの中から相続税の課税対象になる財産とならない財産とを区別する必要があります。
すべての財産が相続税の課税対象となるわけではないため、注意が必要です。
相続税の課税の対象とならない財産については、こちらもご覧ください。
遺産の内容と価値を正確に判断するには、細かい知識が必要になる場面も多いですので、税理士に相談されることをおすすめします。
不動産を活用した相続税対策で注意すること 遺産分割がまだできていない場合の相続税申告