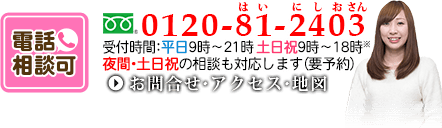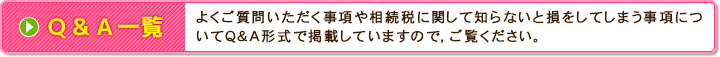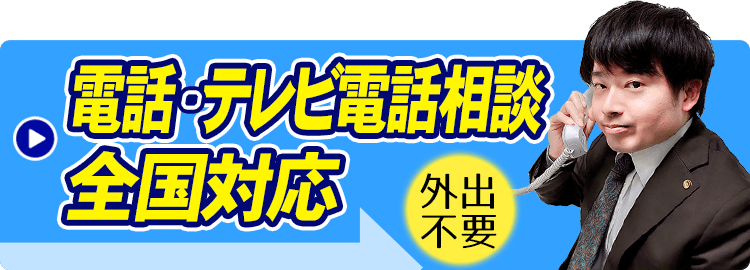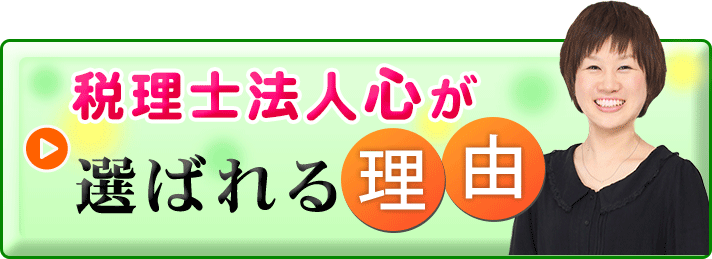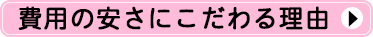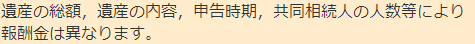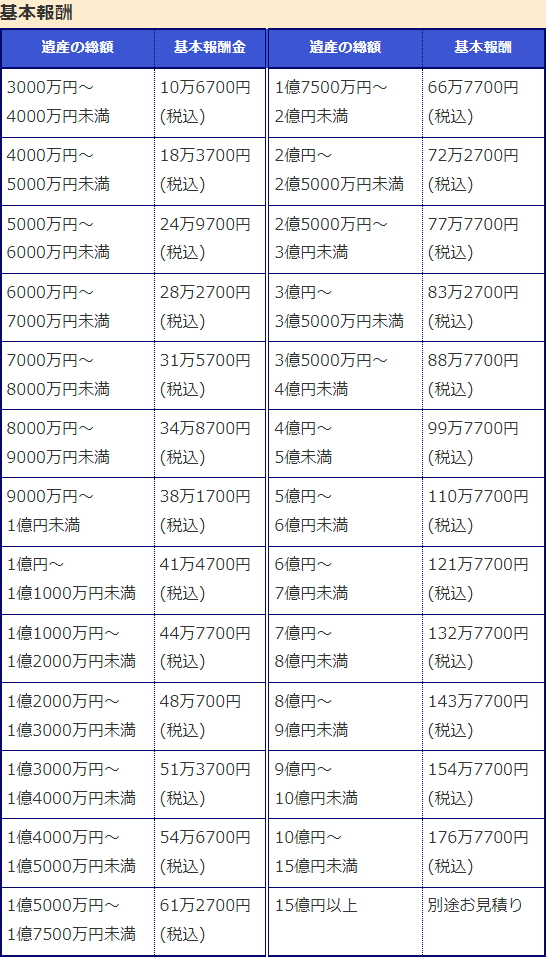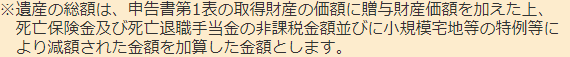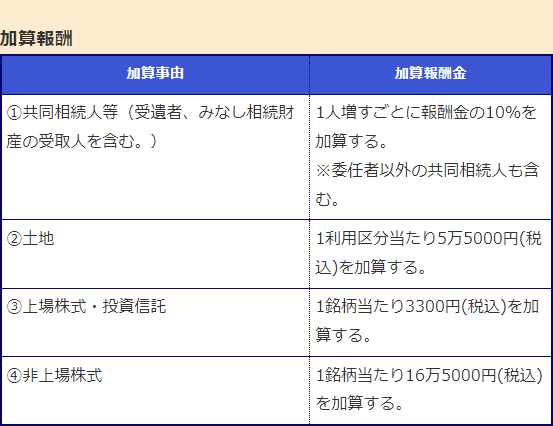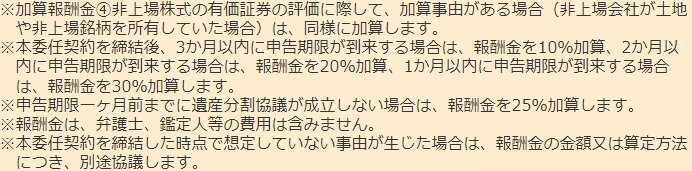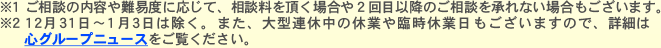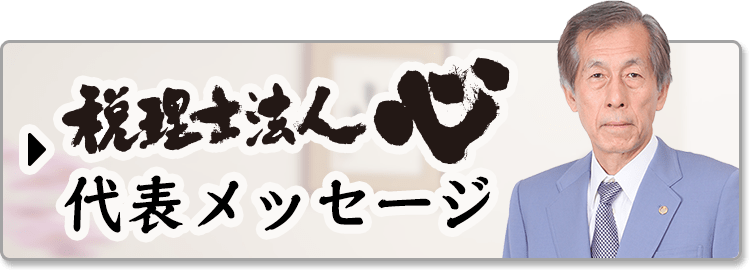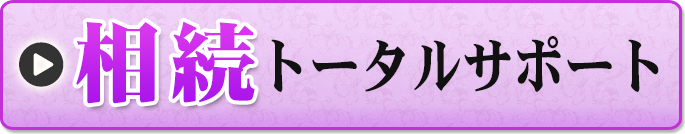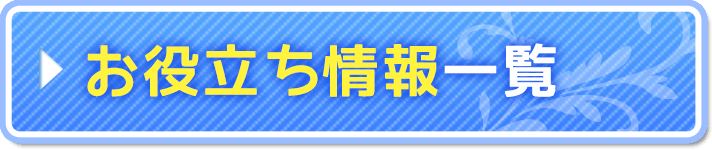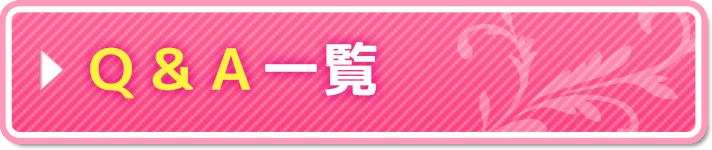「相続税申告」に関するお役立ち情報
相続税申告と不動産の評価
1 相続税申告の際の土地の評価方法
相続税を計算する際、土地の価額は、実際に売却するまで分からないため、国税庁は土地の評価の方法を決めています。
⑴ 路線価がある地域
相続税申告の場面では、国税庁が発表している路線価という指標を使って、土地の価額を決めています。
路線価については、国税庁のホームページをご確認ください。
参考リンク:国税庁・財産評価基準書 路線価図・評価倍率表
路線価が記載された地図には、「この道路に面している土地の、1㎡あたりの価額」が記載されています。
⑵ 路線価がない地域
道路などがあまり整備されていない地域では、路線価は定められていません。
そのため、そういった地域では、倍率方式という方法で、土地の価額を決めます。
具体的にいうと、その土地の固定資産評価額に、一定の倍率をかけた値を、その土地の価額とすることになります。
倍率がどの程度かは、地域や地目によって異なりますが、宅地の場合、多くの地域では、1.1倍となっていることが多いです。
2 相続税申告の際の建物の評価方法
建物についても、土地と同様、実際の値段は売却するまで分かりません。
しかし、それでは建物の価額が分からず、相続税の計算ができないため、国税庁は、固定資産税評価証明書に記載された評価額を、建物の価額とする旨を規定しています。
なお、以下の国税庁のホームページにも、土地や建物の評価方法が記載されておりますので、あわせてご確認ください。
参考リンク:国税庁・土地家屋の評価
3 貸している土地の評価方法
⑴ マンションなどの土地
自己所有の土地に、建物を建て、第三者に貸している場合、その土地のことを貸家建付地といいます。
貸家建付地は、相続税申告の場面では、普通の土地より低い評価額で計算されます。
土地の価額が下がる理由としては、人に貸している以上、所有者はその土地を自由に使うことができなくなるためです。
参考リンク:国税庁・貸家建付地の評価
⑵ 駐車場などの土地
貸家建付地として、評価額が減額されるためには、土地の上に建物が建っていることが必要です。
駐車場のように建物がない土地は、第三者に貸していたとしても、評価額が下がることはありません。
参考リンク:国税庁・貸宅地の評価
4 貸している建物の評価方法
他人に貸している建物は、所有者が自由に使えないため、相続税申告の場面では、評価額が下がります。
参考リンク:国税庁・土地家屋の評価
5 土地の評価額を下げる様々な要素や特例がある
相続税申告の場面では、土地の評価額を下げるための特例があります。
一番多く使われる特例は、小規模宅地等の特例といい、土地の評価額を最大8割下げることができます。
参考リンク:国税庁・相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
その他、特例ではありませんが、土地の形状や地積、地目や土地の周辺状況等、複数の要因によっても、土地の評価を下げることが可能になります。
6 相続税申告時の不動産評価について
このように、土地の評価は、税金のプロである税理士も間違えるほど、専門性が高く複雑です。
そのため、遺産に土地がある場合の相続税評価については、相続税に詳しい税理士にご相談されることをおすすめします。
当法人には相続税を得意とする税理士がいますので、まず一度ご相談ください。
税務調査に入られやすい相続税申告とその対策 土地の相続税評価額を下げる要因