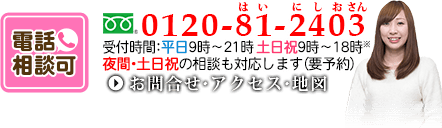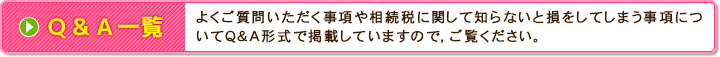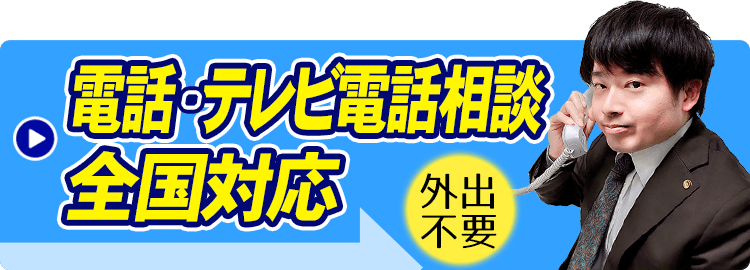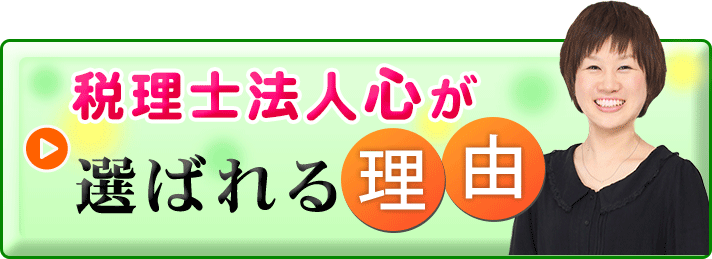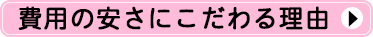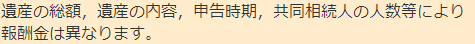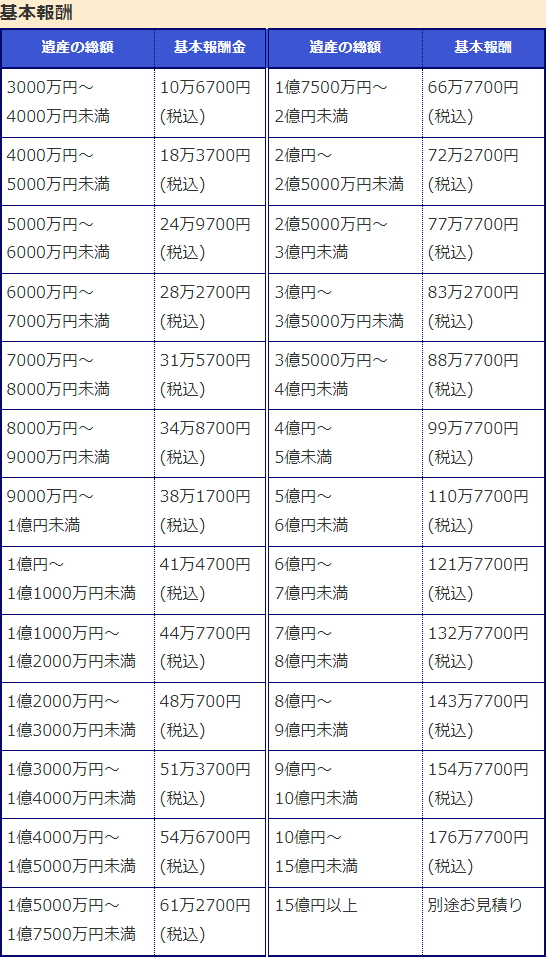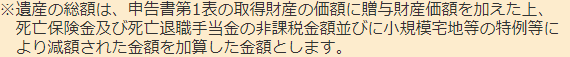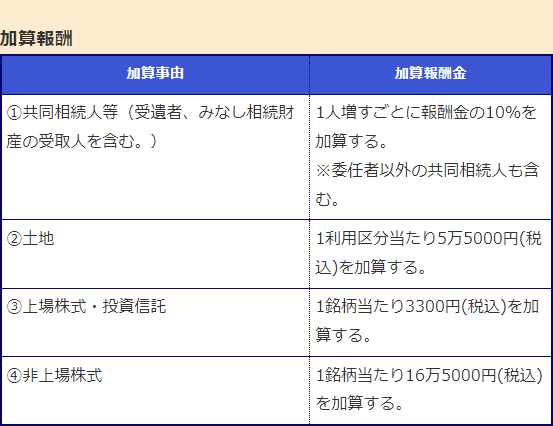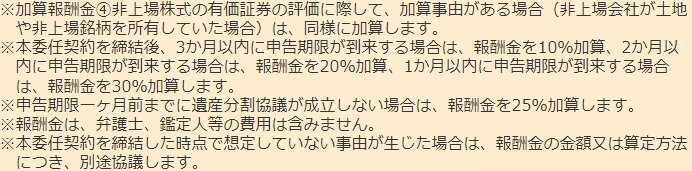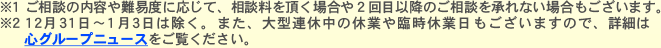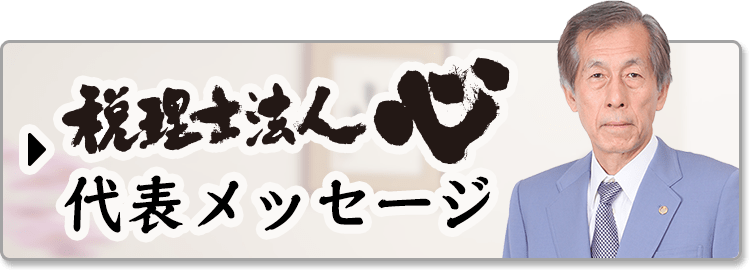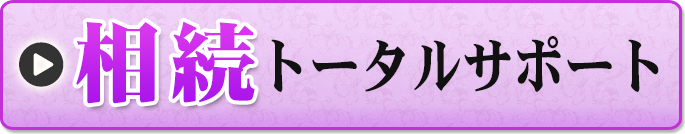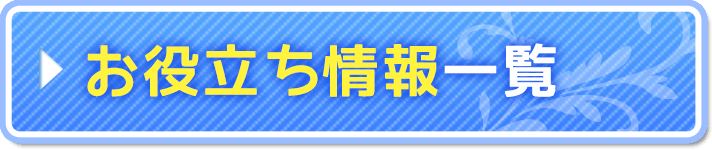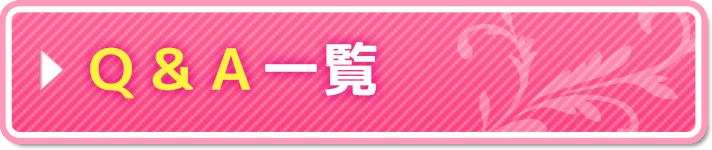「相続税の制度」に関するお役立ち情報
住宅取得資金の特例
1 住宅取得資金贈与の特例
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与により、マイホーム購入、新築、増改築のために支払う金銭(以下、「住宅取得資金」といいます。)を取得した場合において、要件を満たす場合には、一定の金額まで、贈与税が非課税となります。
非課税の範囲については、贈与を受けた人ごとに判断し、省エネ等住宅の場合には1000万円までが非課税となり、それ以外の住宅の場合には500万円までが非課税となります。
「省エネ等住宅」とは、簡単にいうと、省エネ等基準に適合するような家屋で、一定の証明がされたものをいいます。
また、当該住宅取得資金贈与の特例については、贈与を受け取る方が18歳以上であることや、所得が1000万円か2000万円以下であることなど、様々な要件があります。
さらに、見落としやすい要件として、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額をあてて住宅用の家屋の新築等をする必要があり、また、申告期限内(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで)に、住宅取得資金の特例を適用して贈与税の申告をする必要があります。
特に期限については、1日でも期限を過ぎてしまうと、住宅取得資金の特例を使うことは基本的にできなくなり、その場合、高い贈与税を納める必要があります。
なお、本特例の詳細や他の要件等については、以下の国税庁のホームページもあわせてご確認ください。
2 相続税と生前の贈与
相続等により財産を取得した相続人及び受遺者が、その相続開始の3年以内(2024年(令和6年)1月1日以降の生前贈与から、3年の期間を段階的に7年間に延長)に、その相続に係る被相続人から贈与により財産を取得した場合、その贈与により取得した財産の価額が相続税の課税価格に加算されます。
つまり、相続開始の3年以内(2024年(令和6年)1月1日以降の生前贈与から、3年の期間を段階的に7年間に延長)に、被相続人から相続人へ100万円の暦年贈与があれば、被相続人の相続開始時点での預貯金は、その贈与された100万円が減少した金額となっているはずですので、相続税の計算の際には、その100万円を相続財産に加算するということです。
このように、相続開始前の贈与では、相続税の対策にならない場合もあります。
なお、暦年贈与に関する詳細については、以下の国税庁のホームページもご確認ください。
参考リンク:国税庁・贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
3 相続税と住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例
現状として、住宅取得資金の特例は令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間の贈与に適用されますので、相続開始前に生前贈与された財産の価額を相続税の課税価格に加算する期間が、相続開始前3年間から7年間に延長されることに影響するとも考えられます。
もっとも、相続開始の3年から7年以内に、住宅取得資金の贈与を受け、特例の適用を受けた場合には、相続税の計算上、課税価格には加算されません(上記2の国税庁のホームページより、「加算しない贈与財産の範囲」をご参照ください。)。
つまり、通常の暦年贈与と異なり、住宅取得資金の贈与については、特例の適用を受ければ、相続開始直前の贈与だったとしても、相続財産からは除かれ、結果的に相続税対策につながります。
たとえば、住宅取得資金贈与の特例によって、1000万円を子に贈与し、かつ、暦年贈与として追加で110万円の贈与をした場合、これらの贈与が相続開始前3年の贈与であった場合、暦年贈与をした110万円のみが相続税の課税対象に含まれ、1000万円については、課税対象に含まれないことになります。
仮に、1000万円の相続税の非課税効果が200万円の場合、住宅取得資金贈与の特例を使えば、たとえ相続開始直前の贈与であっても相続税を200万円も抑えることができます。
このように、贈与と相続税の関係については、慎重に検討する必要がありますので、一度、税理士に相談することをおすすめします。
相続税の申告・納税をするのは誰か 小規模宅地等の特例で相続人の同意が必要となるケース