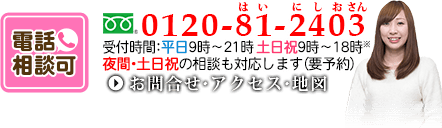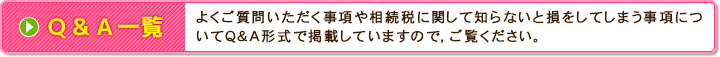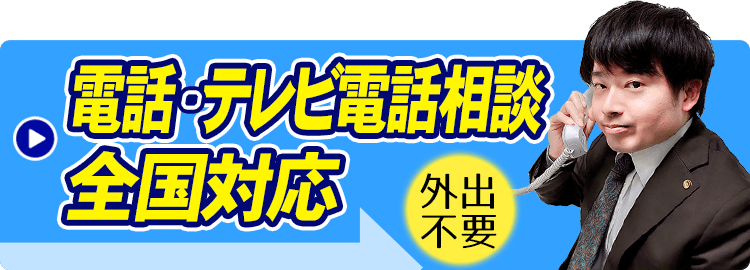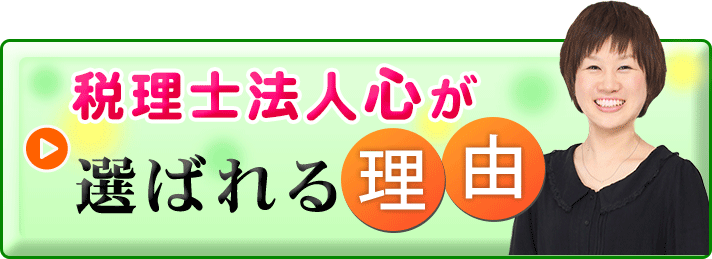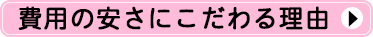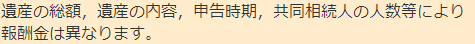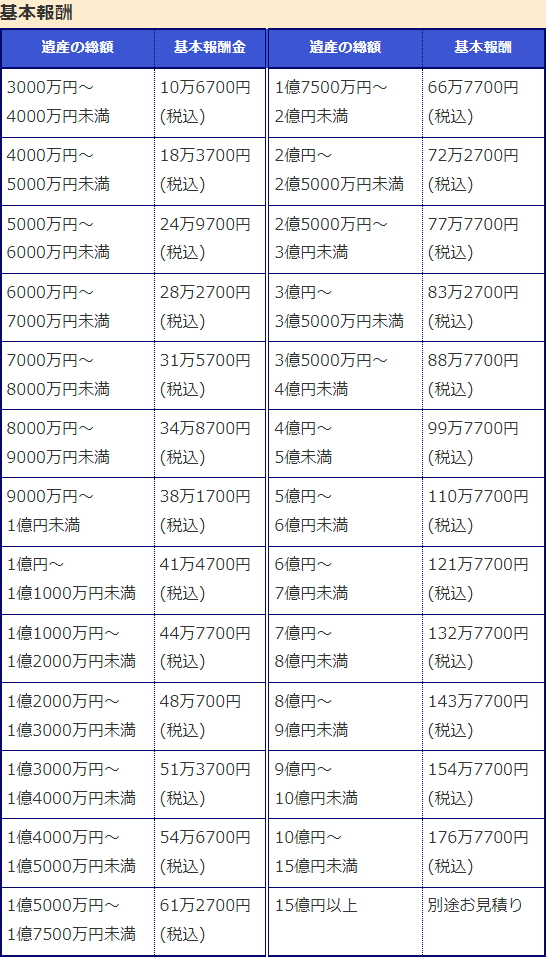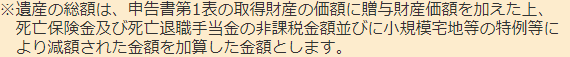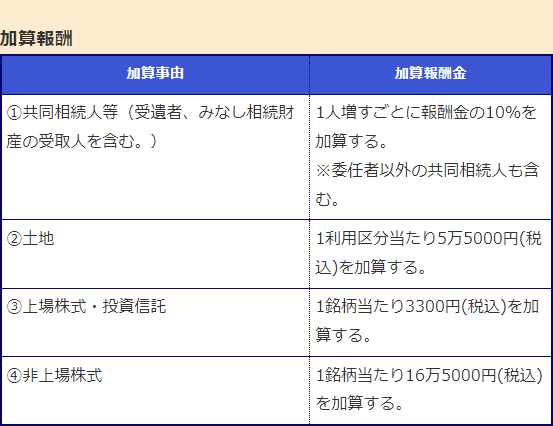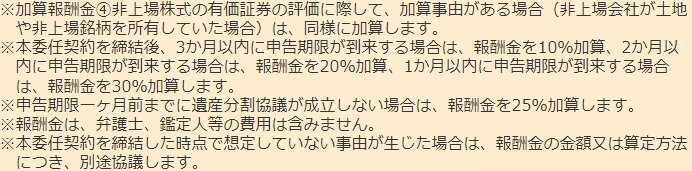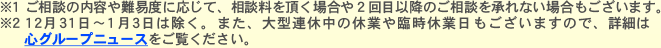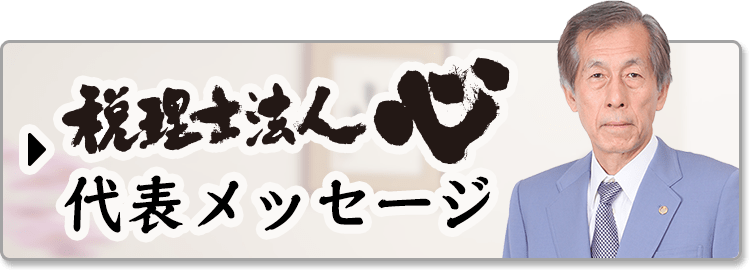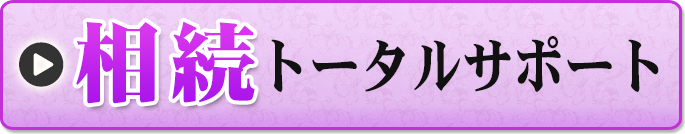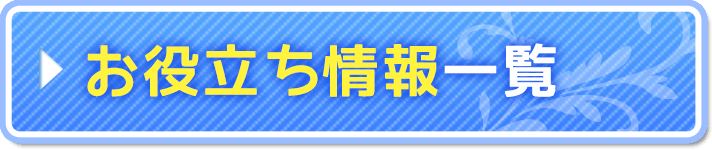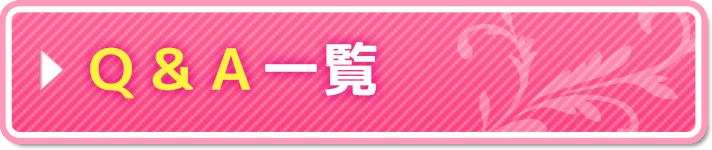「相続税の制度」に関するお役立ち情報
面積の広い土地を相続した場合の相続税
1 土地の評価を下げて相続税を抑えられる可能性がある
面積の広い土地を相続した場合、土地について通常の場合より低く評価できる場合があります。
具体的には、地積規模の大きな宅地に該当すれば、20%前後、評価を減額することができ、仮に20%減額できる場合は、例えば1億円の土地であれば、8000万円として評価することができます。
そもそも、地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては500平方メートル以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1000平方メートル以上の地積の宅地をいいます。
なお、地積規模の大きな宅地については、以下の国税庁のホームページもあわせてご確認ください。
参考リンク:国税庁・地積規模の大きな宅地の評価
2 地積規模の大きな宅地の要件
地積規模の大きな宅地に該当するかについては、いくつかの要件があります。
まず、三大都市圏に所在する宅地については、面積が500㎡以上、それ以外の地域に所在する宅地については、1000㎡以上である必要があります。
なお、三大都市圏のなかでも、愛知県だと名古屋市全域が対象となりますが、岡崎市や豊田市だと、一部地域が対象となり、三大都市圏以外であった場合は、1000㎡以上の面積が必要となります。
次に、地区区分が路線価上、普通住宅地区か普通商業・併用住宅地区になっている必要があります。
なお、対象の土地が倍率地域にある場合は、普通住宅地区内にあるものとして考えられています。
次に、対象の土地が市街化調整区域以外であり、また、工業専用地域以外である必要があります。
また、土地の容積率について、東京都の特別区については、300%未満、それ以外の土地だと400%未満であるなどの必要があります。
また、倍率地域にある場合は、大規模工業用地に該当しない土地である必要があります。
これらが全て問題なければ、地積規模の大きな宅地に該当します。
3 地積規模の大きな宅地の注意点
地積規模の大きな宅地を適用する際にはいくつかの注意点があり、これを間違えてしまうと、本来適用ができないにも関わらず適用してしまい、後日、税務調査に入られてしまうケースや、反対に地積規模の大きな宅地が適用できたにも関わらず、適用しなかった結果、余分に相続税を支払うことになってしまう可能性があります。
⑴ 利用単位ごとに地積規模の大きな宅地を検討する必要がある
まず、地積規模の大きな宅地を適用する際の注意点として、地積規模の要件(三大都市圏は500㎡以上、それ以外は1000㎡以上であること)については、1画地の宅地ごとに評価します。
1画地の宅地というのは、利用単位ごとによって判断します。
そのため、三大都市圏において、隣接する土地の合計面積が500㎡であったとしても、一方は自宅建物を建て、もう一方は、借地として他人に貸している場合、利用区分がそれぞれ異なることになるため、それぞれについて、500㎡を超えている必要があります。
⑵ 分筆して相続すると地積規模の大きな宅地に該当しなくなる場合がある
また、他の注意点として、土地を分割して引き継いだ場合、その土地の面積ごとに判定します。
たとえば、三大都市圏で800㎡の土地がある場合、相続人2人が土地を分筆して400万円ずつで相続した場合、土地の面積が500㎡以下のため、地積規模の大きな宅地には該当しません。
なお、分筆せずに、共有持分で取得している場合は、500㎡を超えるため、他の要件を満たせば、地積規模の大きな宅地に該当します。
他方、被相続人と他人が800㎡の土地を各人2分の1ずつ所有していた場合でも、分筆されていない場合は、他の要件を満たせば、地積規模の大きな宅地に該当します。
⑶ 市街地農地であっても適用できる可能性がある
農地であっても、市街化調整区域ではなく、市街化区域にある農地であれば、地積規模の大きな宅地の要件を満たす場合は、その適用を受けることができます。
なお、市街地農地であっても、宅地へ転用するのに多額の造成費を要し、経済的合理性に欠けている場合や、土地が急斜面などのため、そもそも宅地造成が物理的に不可能な場合は、地積規模の大きな宅地の対象外となります。
参考リンク:国税庁・地積規模の大きな宅地の評価-市街地農地等
マンションを相続した場合、小規模宅地の特例は使えないのか 中村区にお住まいで相続税の相談をお考えの方へ