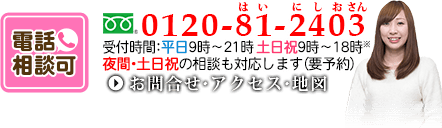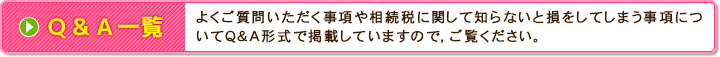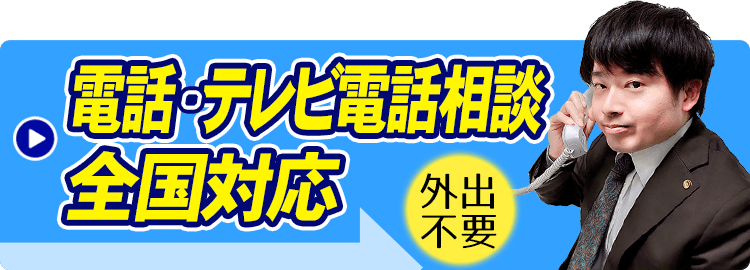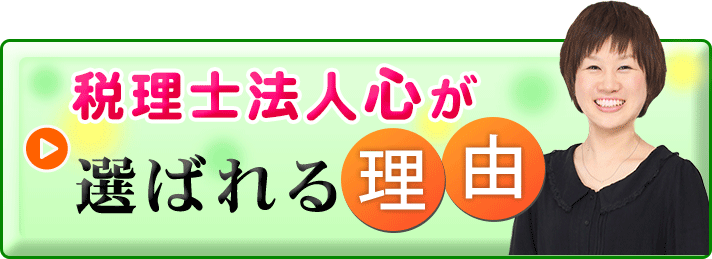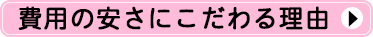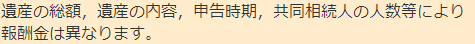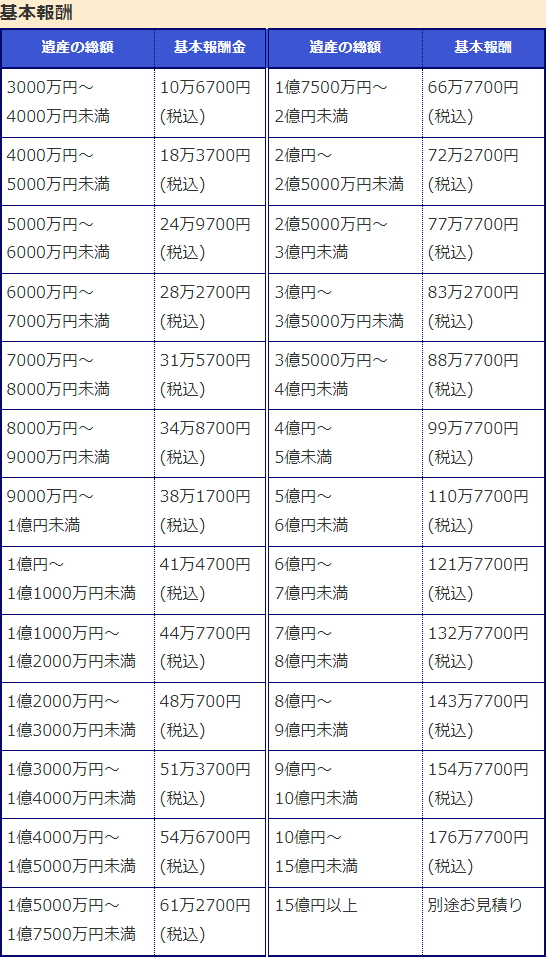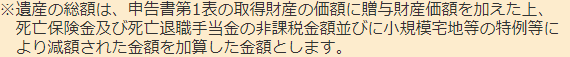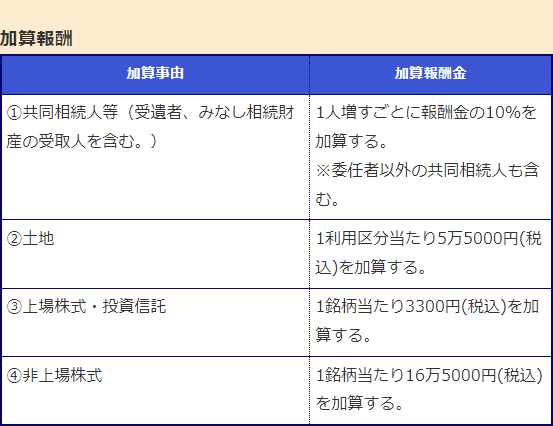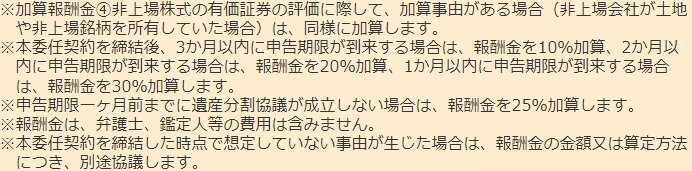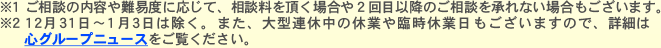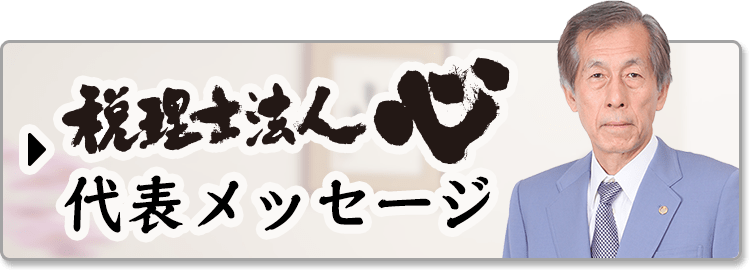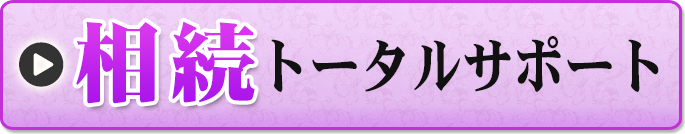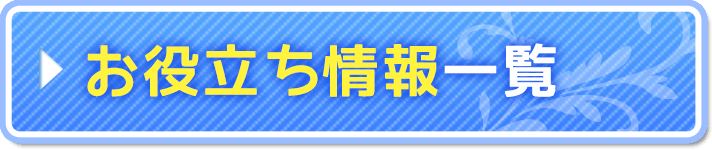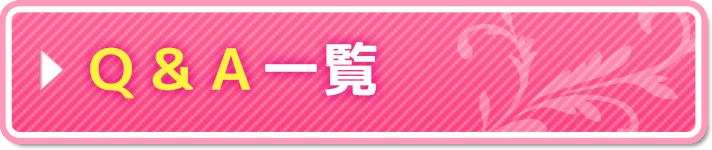「税務調査」に関するお役立ち情報
相続税の税務調査結果に不服がある場合
1 税務調査の結果に不服がある場合の手続き
相続税の税務調査の結果に不服がある場合、①再調査請求、②審査請求、③訴訟という方法をとることができます。
もっとも、これらの方法については期限が設定されており、期限内に手続きを行わなかった場合、不服申立てができない可能性もありますので、注意が必要です。
また、不服申立てを行う場合、基本的に納税は済ませておいた方がよいでしょう。
理由として、仮に不服申立てが認められなかった場合、それまでの延滞税というペナルティも含めて支払う必要があり、場合によっては数百万円もの延滞税となってしまう可能性があるためです。
なお、不服申立ての詳細については、以下の国税庁のホームページもご確認ください。
参考リンク:国税庁・税務署長の処分に不服があるとき
2 税務署長に対し再調査請求をすることができる
まず、税務調査の結果について不服がある場合、税務署長に対し、再度、調査内容の検討を求めることができます。
再調査請求の場合、処分に携わった担当者が再調査請求の担当になることはないため、税務署の判断が変わる可能性があります。
再調査請求は、税務調査の結果に関する処分(構成の請求などの課税処分や差押えなどの滞納処分)の通知を受け取った日の翌日から3か月以内に行う必要があり、期限を過ぎると、再調査請求ができなくなりますので、注意が必要です。
3 国税不服審判所長に対し審査請求をすることができる
また、税務調査の結果について不服がある場合、国税不服審判所長に対し、審査請求(税務署長の判断が正しいのかの確認請求)をすることができます。
再調査請求は、税務署長に対し、再度の調査を求めるものであるのに対し、審査請求は、国税不服審判所というところに、税務調査の結果が法的に正しいのか判断を仰ぐものとなります。
この審査請求については、納税者に不利益となるような変更はされることはなく、基本的に、税務調査の結果の是正が認められるかどうかの判断となります。
また、この審査請求については、再調査請求と同様、期限があり、税務調査の結果に関する処分の通知を受け取った日の翌日から3か月以内か、再調査請求の結果の通知を受け取った日の翌日から1か月以内に審査請求を行う必要があります。
なお、納税者側としては、再調査請求を行わず、いきなり審査請求をすることはできますが、まずは再調査請求をし、その後、審査請求を行うのが一般的ではあります。
4 訴訟を起こすことができる
審査請求の結果(裁決)が出た後、それでも処分に不服がある場合は、地方裁判所に対し、訴訟を提起することができます。
地方裁判所が税務調査の結果について審理し、税務調査の結果について判決をします。
当該判決に不服の場合、高等裁判所に控訴でき、高等裁判所の判決にも不服の場合、最高裁判所に上告することができます。
地方裁判所に対する訴訟の提起については、税務調査の結果が出た後、いきなり行うことはできず、審査請求の結果(裁決)を経る必要があります。
また、訴訟についても期限があり、裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内に訴訟を提起する必要があります。
なお、訴訟まで争った場合、審査請求を経る必要もあるため、最終的な判決が出るまで2年から3年以上かかることがあります。
5 不服申立てについては相続税に強い専門家にご相談を
このように、税務調査の結果に不服がある場合、さまざまな不服申立て手続きがあり、期限内に適切な手続きを行っていく必要があります。
また、不服申立てを行う場合、かなり専門的な税金上の知識や法律上の知識が必要になります。
そのため、税務調査の結果に関する不服申立てをご検討の場合は、不服申立ての期限もありますので、できる限り早めに相続税に詳しい専門家にご相談いただくことをおすすめします。
面積の広い土地を相続した場合の相続税 中村区にお住まいで相続税の相談をお考えの方へ